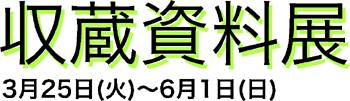
| 福井市自然史博物館ホーム>収蔵資料展2003 |
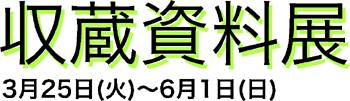
|
|
動物、植物、昆虫、地学などの各分野から、新しく収集した資料や未公開資料、またひつじ年にちなむ資料を公開します。
|
|
限定企画「スクラッチクイズ」実施中! |
|
ではでは、ちょこっとだけお見せしましょう・・・ |
| ひつじ年にちなむ生き物「マアナゴ」 マアナゴという貝の学名はHaliotis (Ovinotis) ovinaで、ラテン語でヒツジを意味するOvisに由来しています。確かに殻はヒツジの角にそっくりです。今回はマアナゴとその仲間のアワビを紹介します。 |

|
| きのこレプリカ「スッポンタケ」 きのこなど、生きている時の状態を保つのがむずかしいものは、実物から型取りして樹脂でそっくりに作った「レプリカ」が資料として役にたちます。今回は5点の資料(スッポンタケ、クリタケ、オオセミタケ、ツチグリ、ブナハリタケ)を公開します。 |

|
| 福井市鮎川産化石「ウソシジミ」 鮎川はおよそ1650万年前の化石が産出し、採集に適した場所でした。しかし、高潮対策などの改良工事のため、その露頭をうめることになりました。この機会に、博物館ではいくつかの化石資料を鮎川で採集しました。写真はウソシジミで、他にビカリア、ゲロイナなどの貝類化石を紹介します。 これらの貝類の仲間で今みられるものは、いずれもマングローブ干潟などにすんでいます。つまり、1650万年前の福井はかなり暖かかったということがわかります。 |

|
| 「ムササビ」はく製と骨格標本 2002年夏に越前町の河原でネズミ取りにかかったムササビが足羽山動物園に保護されました。が、残念ながら手当てのかいなく、死んでしまいました。そのムササビを博物館がもらいうけ、骨格標本として「成仏」させました。博物館所蔵のはく製と一緒に展示し、形を比較できるようにしています。骨からは、じつに様々なことがわかります。なにがわかるかって? それは博物館に来てのお楽しみ・・・ |

|
| 樹木標本「ヌマスギ」 2002年の暮れに、京都大学理学部附属植物園でいくつかの木が伐採されることになりました。かなり大きい木も切ることになったようで、もったいない話です(まあ、大学も独法化やらなんやらでセンセイ方も先が見えないのか、気長に木でも見てまひょかという時代ではないんでしょうかねえ)。 で、この話を博物館が聞きつけ、「どうせ切ってしまうのなら、輪切りをもらおう」ということになり、今回3種の木(ヌマスギ、スズカケノキ、ノグルミ)の輪切りをゆずり受けました。写真はヌマスギで、直径約70センチ、樹齢50年以上です。この展示はさわれるようにしてあります。ぜひ木の皮の様子や、においなどを感じ取ってください。 |

|
| 「エゾイトトンボ」 2002年に和泉村夫婦池で確認されたエゾイトトンボです。県内では、大野市や金津町での生息が確認されていました。今回の和泉村での確認は、新産地記録となります。夫婦池ではマメシジミも見つかり、その標本も展示しています。 |

|
| 「ツツドリ」はく製 2002年8月にツツドリが博物館のガラスに衝突した話は、フォトギャラリーVol.2でもお伝えしました。今回、そのはく製ができあがりました。他にもカワセミ、カケス、モズなどのはく製を展示しています。 野鳥は法律で採集が禁止されていますので、このような事故死の野鳥を集めることは博物館にとって重要な資料収集活動です。もしみなさんもこのような野鳥の事故死を発見した場合は、ぜひ博物館へお知らせください。 |
|
| 特別展プレ展示「火星スケッチ」 今年はなんと5万年ぶりといわれる未曾有の火星大接近の年です。もちろん、この機会をのがす手はありません。博物館では2003年7月20日から「今年の夏は火星に大接近」という特別展を開催します。 そのプレ展示として、博物館で続けてきた火星観測の記録の一部を紹介します。写真は中島孝協力員の火星のスケッチです。小さな天文台の観測でも、地道に継続すれば天文学に大きな役割を果たすと言えます。この夏をお楽しみに! |

|
| その他の展示 ひつじ年にちなむ生き物「アンモナイト」「ヒツジグサ」 斉藤コレクション(福井県産甲虫コレクション) 越前海岸に漂着したアオイガイ 古川田溝氏寄贈図書 |